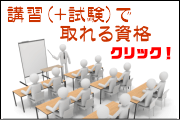公認心理師
公認心理師
公認心理師とは?
公認心理師とは、国民の心の健康の保持増進を適正に業務遂行できるように新しく作られた国家資格です。(現在の民間資格である臨床心理士が公認心理師になるわけではありません。)名称独占資格ですが、今後、必置資格や配置基準などに規定される可能性があります。合わせて、公認心理師は秘密保持義務(法第40条、第41条)が課せられるほか、常に知識及び技術を向上させる努力義務が課せられます。
原則、大学(心理系学部・学科卒業)において、指定カリキュラムを履修する必要がありますが、臨床心理士が大学院卒の学歴を必要とするのと比較して学歴要件が緩やかとなっています。
公認心理師のスキルアップとキャリアアップのために、上級となる分野別の「専門公認心理師」の認定制度を開始予定です。
5分野に別れており、5年ごとの更新制で、更新するためには、必要な条件を満たす必要があります。






その他情報
| 難易度は? | : | ★★★☆☆(普通)。 近年合格率は、66.9%ほど。
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 勉強時間は? | : | 大学院、大学において勉強する必要があるので最低でも4年となります。(経過措置除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 就職は? | : | 医療機関、学校、一般企業など、多種多様の業界で活躍することが可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕事内容は? | : | 保健医療、福祉、教育などのさまざまな分野で、支援を必要とする人々やその家族やなどの関係者に対し、心理に関する心理状態、相談、観察、分析、助言、指導、援助、教育及び情報の提供などを行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||
資 格 概 要
受験資格
以下の受験資格に該当し、かつ受験資格に関する所定の証明資料を提出できること。
- 日本臨床心理士資格認定協会が認可する第1種指定大学院(修了後の心理臨床経験不要)を修了し、受験資格取得のための所定条件を充足している者。
- 日本臨床心理士資格認定協会が認可する第1種指定大学院を修了し、修了後1年以上の心理臨床経験を含む受験資格取得のための所定条件を充足している者。
- 日本臨床心理士資格認定協会が認可する第2種指定大学院を修了し、修了後1年以上の心理臨床経験を含む受験資格取得のための所定条件を充足している者。
- 日本臨床心理士資格認定協会が認可する第2種指定大学院を修了し、修了後2年以上の心理臨床経験を含む受験資格取得のための所定条件を充足している者。
- 学校教育法第65条第2項に基づく大学院において、臨床心理学またはそれに準ずる心理臨床に関する分野を専攻する専門職学位課程を修了した者。
- 諸外国で上記1.または3.のいずれかと同等以上の教育歴および日本国内における2年以上の心理臨床経験を有する者。
- 医師免許取得者で、取得後2年以上の心理臨床経験を有する者。
●受験資格の特例について
経過措置として、法施行から5年間については以下の通り、すでに必要な学科を修了し、業務を行っている方や現在大学及び、大学院に在籍する方なども受験資格が与えられます。
- 法が施行される前に大学院を修了していて、国が定める科目を履修し終えている者。
- 法が施行される前に大学院に入学していて、国が定める科目を履修して修了できる者。
- 法が施行される前に大学に入学していて、大学で必要な科目を履修した者、それに準ずる者で、定められる大学院に進学し修了する者。
- 法が施行される前に大学に入学していて、大学で必要な科目を履修して卒業した者、それに準ずる者で、一定の施設で一定期間実務を行った者。
- 上記1〜4に当てはまらなくても心理に関する業務の経験が5年以上ある者で、国が指定した講習会を受講した者。
経過措置終了後は、以下のとおりとなります。
- 大学・大学院の両方で、必要な科目を履修し修了した者。
- 大学で必要な科目を履修した人、またはそれに準ずる人で、一定期間、一定施設で実務に従事した者。
- 主務大臣が上記 1. に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者。
試験内容
多肢選択方式(5肢または4肢:150問〜200問程度) 心理師として具有すべき知識及び技能
- ① 公認心理師としての職責の自覚
- 公認心理師の役割
- 公認心理師の法的義務及び倫理
- 心理に関する支援を要する者(以下「要支援者」という。)等の安全の確保と要支援者の視点
- 情報の適切な取扱い
- 保健医療、福祉、教育その他の分野における公認心理師の具体的な業務
- ② 問題解決能力と生涯学習
- 自己課題発見と解決能力
- 生涯学習への準備
- ③ 多職種連携・地域連携
- 多職種連携・地域連携の意義及びチームにおける公認心理師の役割
- ④ 心理学・臨床心理学の全体像
- 心理学・臨床心理学の成り立ち
- 人の心の基本的な仕組みとその働き
- ⑤ 心理学における研究
- 心理学における実証的研究法
- 心理学で用いられる統計手法
- 統計に関する基礎知識
- ⑥ 心理学に関する実験
- 実験計画の立案
- 実験データの収集とデータ処理
- 実験結果の解釈と報告書の作成
- ⑦ 知覚及び認知
- 人の感覚・知覚の機序及びその障害
- 人の認知・思考の機序及びその障害
- ⑧ 学習及び言語
- 人の行動が変化する過程
- 言語の習得における機序
- ⑨ 感情及び人格
- 感情に関する理論と感情喚起の機序
- 感情が行動に及ぼす影響
- 人格の概念及び形成過程
- 人格の類型、特性
- ⑩ 脳・神経の働き
- 脳神経系の構造と機能
- 記憶、感情等の生理学的反応の機序
- 高次脳機能の障害と必要な支援
- ⑪ 社会及び集団に関する心理学
- 対人関係並びに集団における人の意識及び行動についての心の過程
- 人の態度及び行動
- 家族、集団及び文化が個人に及ぼす影響
- ⑫ 発達
- 認知機能の発達及び感情・社会性の発達
- 自己と他者の関係の在り方と心理的発達
- 生涯における発達と各発達段階での特徴
- 非定型発達
- 高齢者の心理社会的課題と必要な支援
- ⑬ 障害者(児)の心理学
- 身体障害、知的障害及び精神障害
- 障害者(児)の心理社会的課題と必要な支援
- ⑭ 心理状態の観察及び結果の分析
- 心理的アセスメントに有用な情報(生育歴や家族の状況等)とその把握の手法等
- 関与しながらの観察
- 心理検査の種類、成り立ち、特徴、意義及び限界
- 心理検査の適用、実施及び結果の解釈
- 生育歴等の情報、行動観察、心理検査の結果等の統合と包括的な解釈
- 適切な記録、報告、振り返り等
- ⑮ 心理に関する支援(相談、助言、指導その他の援助)
- 代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史、概念、意義及び適応
- 訪問による支援や地域支援の意義
- 要支援者の特性や状況に応じた支援方法の選択、調整
- 良好な人間関係構築のためのコミュニケーション
- 心理療法及びカウンセリングの適用の限界
- 要支援者等のプライバシーへの配慮
- ⑯ 健康・医療に関する心理 学
- ストレスと心身の疾病との関係
- 医療現場における心理社会的課題と必要な支援
- 保健活動における心理的支援
- 災害時等の心理的支援
- ⑰ 福祉に関する心理学
- 福祉現場において生じる問題とその背景
- 福祉現場における心理社会的課題と必要な支援方法
- 虐待、認知症に関する必要な支援
- ⑱ 教育に関する心理学
- 教育現場において生じる問題とその背景
- 教育現場における心理社会的課題と必要な支援
- ⑲ 司法・犯罪に関する心理学
- 犯罪、非行、犯罪被害及び家事事件に関する基本的事項
- 司法・犯罪分野における問題に対して必要な心理的支援
- ⑳ 産業・組織に関する心理学
- 職場における問題に対して必要な心理的支援
- 組織における人の行動
- ㉑ 人体の構造と機能及び疾病
- 心身機能、身体構造及びさまざまな疾病と障害
- 心理的支援が必要な主な疾病
- ㉒ 精神疾患とその治療
- 代表的な精神疾患の成因、症状、診断法、治療法、経過、本人や家族への支援
- 向精神薬をはじめとする薬剤による心身の変化
- 医療機関への紹介
- ㉓ 公認心理師に関係する制度
- 保健医療分野に関する法律、制度
- 福祉分野に関する法律、制度
- 教育分野に関する法律、制度
- 司法・犯罪分野に関する法律、制度
- 産業・労働分野に関する法律、制度
- ㉔ その他(心の健康教育に関する事項等)
- 具体的な体験、支援活動の専門知識及び技術への概念化、理論化、体系化
- 実習を通じた要支援者等の情報収集、課題抽出及び整理
- 心の健康に関する知識普及を図るための教育、情報の提供
合格基準
満点中、60%程度以上の正答率で合格となります。
身体上の障害等に係る特別措置について
配慮申請受付期間内に必要書類を提出してください。
障害者手帳(視覚・聴覚・肢体不自由等)の有無、障害の種類や程度に関わらず、以下のような場合は配慮申請が必要です。試験時間中に、補飲食、補聴器や人工内耳の使用、糖尿病の血糖値測定器の使用、サングラスの使用、眼鏡型でないルーペの使用、松葉杖の使用、帽子の着用、試験室内(自席)での水分の補給、服薬、目薬の使用、体型による可動式の机・椅子を希望する場合には、配慮申請が必要となります。
なお、試験会場、試験室の指定についての申込みはできません。
※
申請には受験上の配慮事項が必要な理由が明記された「医師の診断・意見書(指定の様式に限る)」、「身体障害者手帳等の写し」等の提出が必要となります。
※
受験上の配慮事項は、すべての受験者の公平性の観点から障害者福祉の専門家である医師等の審査を経て決定しますので、ご希望に添えない場合があります。
配慮申請書に必要事項を記入して、必要書類を同封し、受験申込書とは別に以下の宛先まで簡易書留で郵送してください。
〒112-0006
東京都文京区小日向4-5-16 ツインヒルズ茗荷谷10階
一般財団法人日本心理研修センター 配慮係
願書申込み受付期間
12月上旬〜下旬頃まで
試験日程
3月上旬頃
受験地
東京、大阪
受験料(税込み)
28,700円
合格発表日
3月下旬頃
公認心理師試験に合格した者が、一般財団法人日本心理研修センターに所定の事項についての登録申請を行うことで、「公認心理師」となることができます。
ただし、以下の者は、登録を受けることが出来ません。
- 成年被後見人又は被保佐人
- 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- この法律の規定その他保健医療,福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 公認心理師の登録を受けようとするときは,登録免許税法(昭和42年法律第35号)に基づき,登録免許税:15,000円を納付する必要があります。
- 公認心理師の登録を申請するときは,登録免許税のほか登録手数料:7,200円を払い込む必要があります。
受験申込・問合せ
- 試験案内専用電話 03-6912-2655
- 公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会 03-3817-0020
- 公認心理師試験に関するお問い合わせ 03-5645-8462
- 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 公認心理師制度推進室
03-5253-1111(内線 3112、3113)