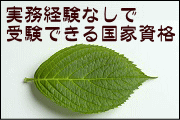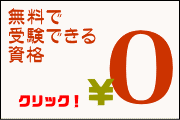土壌環境監理士
土壌環境監理士
土壌環境監理士とは?
土壌環境監理士とは、土壌・地下水汚染に係る調査、対策等に関する正しい知識・判断力を備え、土壌地下水環境保全分野で社会に信頼されうる人材を認定する資格です。
資格の有効期間は、土壌環境監理士試験合格の日の翌月1日から3年間で、更新を行わない場合、資格が失効します。更新するには、有効期間が満了する日の2か月前から期間満了日までに、資格の更新申請をするためには、センターが主催、共催、後援、協賛するなど、センターが協力関与しているセミナー、講習会、ワークショップ、報告会、発表会、出版物等でセンターが認めたものに3回以上参加(聴講、発表、投稿すること)する必要があります。更新により、3年間資格が有効となります。


その他情報
| 難易度は? | : | ★★★★☆(やや難しい)。 近年合格率は、33.3%ほど。 環境系資格では技術士に次いで難関の資格。 |
| 就職は? | : | 調査コンサルティング会社や建設関係、プラントメーカー、分析業等に従事している人が取得を目指す資格。いかんせんネームバリューが低いので求人自体はあまりない。 |
| 仕事内容は? | : | 土地利用計画に基づいた調査、修復計画、予算の提案、土壌汚染調査、修復工法の計画と施工、計測・品質及び施工管理を行います。 |
資 格 概 要
受験資格
以下の(1)実務経験と(2)資格等を同時に満たしていることが受験資格となります。
(1)実務経験
- 土壌・地下水汚染の調査・対策に関する実務経験が3年を超える者
- 大学院の土壌・地下水汚染調査・対策の研究期間が3年を超える者
- 1及び2の期間の合計が3年を超える者
(2)資格等
- 1.土壌汚染対策法で定める技術管理者試験合格者
- 2.技術士登録者であって、次に定める技術部門・選択科目の者
- 建設部門(選択科目:「土質及び基礎」又は「建設環境」)
- 応用理学部門(選択科目:「地質」)
- 環境部門(選択科目「環境保全計画」又は「環境測定」)
- 衛生工学部門(選択科目:廃棄物管理)
なお、技術士の技術部門、選択科目で統合、名称変更等があったものは、現技術士制度に引き継がれた技術部門、選択科目に読み替えるものとします。
- 3.水質関係第1種公害防止管理者試験の合格者
- 4.土壌・地下水汚染に関する研究で学位を得た博士号(工学)取得者
- 5.一般社団法人土壌環境センターの土壌環境保全士の資格を継続して6年以上保有している者
試験内容
●筆記試験(記述式/3時間)
- ① 現場作業者と周辺環境の安全に関する知識と配慮
- ② 土壌・地下水汚染関連法および関係する法律等についての知識
- ③ 土壌・地下水汚染による環境リスク(健康、生活)の概念についての理解
- ④ 土壌・地下水汚染の調査・対策実施における周辺環境保全のための手法についての理解
- ⑤ 水文・水理地質および汚染物質等の基礎知識
- ⑥ サイトの特性、調査の目的を踏まえた適切な調査計画の立案
- ⑦ 調査実施に必要な機器に関する知識と適切な調査・分析方法の選定
- ⑧ 汚染実態等に関する適切な判断
- ⑨ 条件(費用配慮、環境配慮を含める)に応じた適切な対策手法の立案
- ⑩ 対策工法についての知識
- ⑪ 浄化完了を適切に確認するために必要な知識
- ⑫ 住民、施主、施工者、行政とのコミュニケーションをとる方法についての知識
●面接試験(15分)
筆記試験の内容に関する口頭試問(土壌環境監理士にふさわしい経験と業務遂行能力の有無)
願書申込み受付期間
6月上旬〜7月下旬頃まで
試験日程
●筆記試験
9月上旬頃
●面接試験
11月中旬頃
受験地
東京
受験料(税込み)
18,850円(登録手数料:10,470円が別途必要)
国家公務員あるいは地方公務員の方の受験料は、免除
合格発表日
●筆記試験
11月上旬頃
●口述試験
12月
合格後の更新について
土壌環境監理士の登録有効期間は初回の登録は認定日より3年間、以降は有効期限の翌日から3年間です。
更新するためには、土壌環境保全士リフレッシュ講習の受講、または、レポート等の提出による登録更新申請(登録手数料:10,470円)が必要になります。
期間内に上記の条件を満たさない場合は資格が「一時停止」となり、実施団体HPにも「資格停止中」公表されます。また、資格停止後、引続き2回上記条件を満たさなかった場合は、資格が失効します。
資格停止中に上記条件(土壌環境保全士リフレッシュ講習の受講、または、レポート等の提出による登録更新)を満たすことで、資格が有効となります。
受験申込・問合せ
一般社団法人 土壌環境センター 資格制度事務局 03-5215-5955